「雪国」・・・ではありませんが
大分肌寒くなってきました。
作業着の中はヒートテックが活躍し始めます。
改めてこんにちは!
大工工事部のながともです。
先日現場で一服の際に足下に転がっていたものを
覗いてみました。

一見別世界に誘われそうな筒状の物体。
正体は
・
・
・
・
・
・
・
・
・

写真中央に写っている黒いパイプ状のモノです。
これは「音ふうじ」です。
水道の排水管をつつみ、管の中を流れる水の音を軽減する為のものです。
筒の内側はフェルト状になっており、音を吸収するという事です。
何事も
「へぇ〜この中はこうなっているんだ」
と、自分で発見するのは楽しいです。
次はどんな発見があるかと楽しみにしつつ・・・・
明日も現場に行ってきます。

こんにちは!
大工工事部のながともです。
最近玄関を開けると
金木犀の香りがします。
夜、大分涼しくなってきて
いよいよ秋本番といったところでしょうか?
以前お世話になった住宅の現場での
できごとなのですが、、、
お施主様よりも先に住んでしまう
「せっかちさん」がおります。
彼です。

仮設トイレの壁面で
よく見かける光景なのですが
カモフラージュなのか
居心地がいいのか、
定かではありませんが
すっぽり収まってるのを見つけると
なんか微笑ましいです。
住めば都ってこういうことなのでしょうか?
この現場もお施主様にとって
かけがえのない
「都」になるよう願いつつ・・・・
明日も現場に行ってきます!

こんにちは!大工2年生の内藤です。
相変わらず久し振りの更新となってしまい、すみません…
気が付けば8月もあっという間に終わり、既に秋が来たかのような日々が続いていますが、皆様、夏は十分に満喫されましたでしょうか?
かくいう僕は、今年は資格勉強に追われて、夏らしいことはほとんど何もできずに終わったのですが…(笑)
そんな自分にも、夏の思い出、一つだけありました。
それは、8月頭の現場でのこと…
現在施工中のお施主様の住宅から、近くで行われる花火大会の様子がよく見えるということで、お施主様から「ぜひ皆さんも一緒に、2階から見ましょうよ!」というお誘いを頂いてしまったのです。
当日は、大工、設計、営業と何名もの社員をお招きいただき、食べきれないほどの料理やお酒までご用意していただいて、とても賑やかな宴会となりました。

そして、花火が始まる頃合いを見て、電気を消して、皆で窓から花火見物…
本当に、想像していた以上に近くからの見物でした!
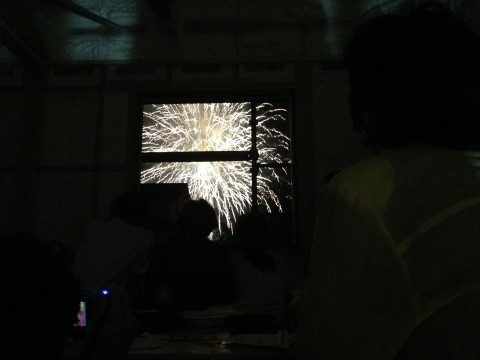
僕がこの夏花火を見たのは、結果的にこの日の一度きりとなったのですが、それでも十分満足できるほど、とても充実した花火見物会でした。
このような素敵な機会をご提案・ご提供してくださったI様、改めまして、本当にありがとうございました。
花火見物会場となりました通称「花火の間」、
現在、枠付けや石膏ボード張り等、鋭意施工中ですので、ぜひ完成と来年の花火大会を楽しみになさっていてください!(笑)
<おまけ写真 その1>
仲良く寄り添って花火を見る、先輩大工お三方

<おまけ写真 その2>
お施主様のワンちゃんと戯れる原田さん


こんにちは!
大工工事部のながともです。
現場で左官屋さんやクロス屋さんが
すき間やデコボコ面をならすために
セメントやパテを塗って平らにしているのを見て
今日は夏に必ずやっていることを
ひとつご紹介します。
女性だからなのか分かりませんが
一緒に仕事をする先輩大工から
100%聞かれるのが・・・
「自炊してるの?」
という質問。
してます!(帰宅して体力的に余裕があれば・・・)
という返答。
「へぇ、得意料理は?」
というお決まりの切り返し。
私は自信もって言えるのはこれです。

あっ・・・植木鉢じゃないです。
ぬか漬けです。
社会人になって母から分けてもらい
夏には必須アイテムです。
(冬でもいけますがキュウリが美味しい時期が夏なので)
もちろん毎日ぬかを混ぜれば混ぜる程
おいしくなるのですが
このように
野菜を埋めて・・・
何事もなかったように
ぬか床を左官屋さん達みたいにならして・・・
冷蔵庫にいれれば2、3日でいい具合に漬かります。
(野菜の皮をむいて、一晩で漬かるようにしたり、塩を加えたり調整できます。)
市販の「いりぬか」を探すと
自分で一から作る事も可能なので
夕飯の一品に困っている人はぜひ。
得意料理とはいいつつ
「これって料理か?」
というふと気づいた自分はさておき・・・・
ひとまず、にんじんを漬けました。
母が作ってくれたぬか漬けの味には
まだ到底及ばないですが
仕事も料理も修行!修行!!
と気を引き締めて
明日も現場にいってきます!

こんにちは。渡邊です。
早速ですがこの金物をご存知ですか?

「イナゴ釘」と言います。昆虫のイナゴに似ているからその名前がついたとか。
この金物、取り扱っている道具屋が少なく、ネットか昔からやっている道具屋にしか置いてありません。
運良く買えたわけですが店の奥のほうにほこりをかぶって置いてありました。
それほど現在では使われなく必要とされていないのでしょう。まさに絶滅危惧種です。
これは羽重天井に使います。

どこに使われているかわかるでしょうか?
天井裏から見るとこんな感じです。

竿縁(写真で言うと横木の部材)の箇所にはビスで固定しています。
竿縁と竿縁の間にはビス固定ができない。
そこでイナゴ釘を使い上の天井板が反って隙間が開かないように押さえつけてあります。
何事も釘で固定していた昔と違い、
現在では無垢材を確実に締め付けて固定することができるビスが主流なので、イナゴ釘を使用しないこともあるとか。
しかし、今回この天井を任せてもらえることにあたり、
確実に丁寧にやるだけでなく、先代の大工が残してきた技法を今後何十年後の大工さんに伝えていく一人でありたいので親方に頼み使わせてもらいました。

仕上がると天井の仕事は天井裏に入らない限り見ることはできません。
どうやって作ったのかは仕事した本人しかわからないことです。
見えないからこそ何か問題が出たときには原因の把握が難しいです。
だからこそ自分がやるからにはとことんやる!と決め取り組みました。
昔に比べると工具の進化で効率、作業のしやすさは数年間で格段に上がりました。
それを代償に失っていく技術もあると思います。
僕も大工になって4年目になります。新人のうちから工具が与えられ、楽をしてきた一人です。
当時は覚えることがたくさんでがむしゃらにやってきました。
現在では家作りの流れの中である程度の仕事が任される年代になりました。
10コ上の上司が4年目に身に付けた能力と僕の今の能力は同じかと考えると、そこは確実に劣っていると考えるようになりました。
最近では簡単にやれている仕事は昔はどうやっていたのだろうと考えながら仕事しています。
残していかなくていい技術なんてないと思います。
まだまだ一人前にはほど遠く知らないことも多いです。
今までの大工がやってきたことを学んだ上で僕の大工をしていこうと思います。
書いていて熱くなってしましました、、、それではまた。
